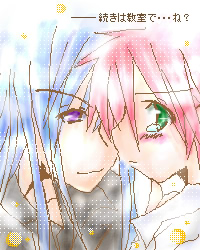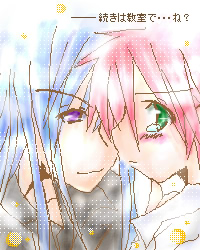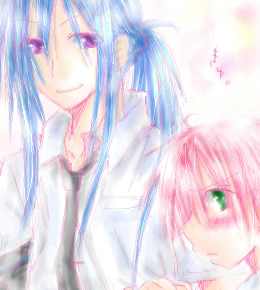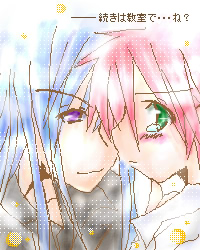
|
| 職員室でイタズラ★/りんご
|
ざわざわと独特の雰囲気が漂う放課後。
普通なら何の用もない生徒は、わざわざ貴重な放課後に職員室になど訪れはしないだろう。
けれど呼び出されたというのなら話は別で。
いつもの如く、今日もまた望は担任の教師に呼び出されてしまっていた。
「失礼します・・・あの、楊ぜん先生は・・・」
「望くん」
ざわつく職員室の中では望の小さな声は掻き消されてしまうかに思えたが、楊ぜん----望の担任教師にはしっかり届いていた。
自分の席から小さく手招きし、望を呼び寄せる。
それを見て望もぱっと顔を輝かせて、てててと楊ぜんのところへ向かっていった。
「先生、今日は何の用事かのう?」
「このプリントを渡そうと思ってね・・・」
クラスの人数分あるプリントの束を渡される。
そこには「夏休みのくらし」と書いてあり、あぁもうすぐ・・・と思ったところで望の思考は中断を余儀なくされた。
いつのまにか楊ぜんの手が望のおしりに回っており、そこをゆっくり撫で上げている。
ここは先生がたくさんいる職員室。
望は身を引き逃げようとするが楊ぜんは離してやらない。
「先生・・や・・・・っ」
「しっ。大人しくしてないとばれてしまいますよ?」
「おしり・・・やなのだ・・・ぁ」
「ホントに望は感度がいいですね・・・」
必死で身を捩る望をしり目に、楊ぜんは楽しそうにクスッと微笑む。
楊ぜんの席は壁側の一番角で、ばれる心配はない。
しかもちゃっかりこの行為が見えないようにプリントでさりげなく隠したりしていた。
これが初めての事ではないのだ。
しょっちゅう職員室に呼び出されてはこうして楊ぜんにイタズラされていた。
しかも楊ぜんの担当科目は理科で、週末は必ず理科室に呼び出されてもっとイタズラされてしまうのである。
最初は何が何だか分からなかった望だが、これが気持ちイイことだと知ってからは何もいわない。
ただ恥ずかしくて俯くだけ。
なにより、全校生徒、先生、保護者、PTAさえ皆虜にしてしまうその美貌で微笑まれてしまえば望には抵抗することが出来なかった。
「前も触って欲しい?」
「・・・・・・・う・・・ん」
「フフッやらしいですね望は。ここは職員室なのにそんなこと言うなんて」
「だってぇ・・・」
「・・・可愛い」
可愛いおしりを執拗に撫で回され望の中心は熱くなりかけていた。
もういつものように触ってもらうことしか考えられなくて。
涙目になり始めた望に楊ぜんはやっと手を離し、存在を主張し始めたモノを隠すように望にプリントを持たせる。
「じゃあ望くん、コレちゃんと教室に届けてくださいね」
「せんせぇ・・・」
熱が引かない身体がもどかしく、望がねだるように楊ぜんを見つめる。
桃色に染まった柔らかいほっぺに微笑み、楊ぜんは小声でそっと囁いた。
----続きは教室で・・・ね?
この甘い囁きにも敵わない。
望はこくっと頷くと素直に自分の教室に向かっていった。
可愛い望に、その後ろ姿を楽しそうに眺めていた楊ぜんは、教室の暑さを予想して扇風機でも持っていくか・・・と立ち上がった。
今年の夏は例年以上に暑くなりそうな予感------
|
|